更新日: 2024年6月1日
広報いちかわ6月1日号 特集
特集1:人とペット 支えあって幸せに暮らそう
特集2:食べて健康 子どもから大人まで年代別に食事のポイントをご紹介
[特集]目次
人とペット 支えあって幸せに暮らそう
ペットは家族の一員や人生のパートナーとして扱われている一方で、ペットを原因とする近隣とのトラブル、犬にかまれる事故などの問題があります。人とペットが心地よく暮らすために、ペットの飼い方について正しい知識を持ち、周囲の人々と共に考えていきましょう。今回は、犬と猫についてお伝えします。
問い合わせ=TEL047-712-6309自然環境課
犬・猫との幸せな暮らしのために活動している方の声を聞きました
犬を飼う時は、慎重に考えて

私たちGUNDOG RESCUE Companion Animal Club Ichikawa(CACI)は、中・大型犬を中心に保護し、譲渡会を通じて新たな飼い主を見つける活動をしています。保護犬の存在をより多くの人に知っていただき、一匹でも多くの保護犬が幸せになることを願っています。
犬が保護される背景には、飼い主の年齢や転居の関係で飼育が困難になってしまう場合など、さまざまな理由があります。これから犬を飼う方には、自分のライフスタイルに合っているか、最期まで世話ができるかを慎重に考えていただきたいです。


受け入れる心が大切

私たちはCACIの譲渡会に参加し、はなちゃん、ひなちゃんをお迎えしました。週末には一緒に海に行くなどアクティブな毎日を送っており、犬たちからたくさんの幸せをもらっていると実感しています。
保護犬にはそれぞれ過去があり、置かれていた環境によっては、その時の不安や恐怖を抱えたままの場合もあります。はなちゃんも捨てられた経験のせいか、最初は警戒心が強かったのですが、徐々にリラックスしてくれるようになりました。
里親になる方は、お迎えする犬のバックグラウンドを全て受け入れ「大切な家族として一緒に幸せになっていく」という気持ちがとても大切だと思います。
犬の譲渡会を開催します
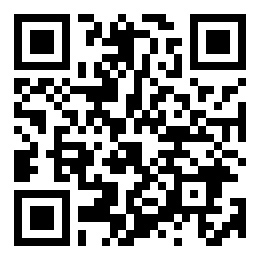
CACIが犬の譲渡会を開催します。犬を迎えたい方は予約なしで参加できます。詳しくは右記2次元コードで確認してください。
日時=6月16日(日曜)正午~午後4時、雨天の場合は23日(日曜)に延期
場所・会場=塩浜ドッグラン
問い合わせ=TEL047-712-6309自然環境課
保護猫を迎え、人生がより豊かに

飼っていた猫が亡くなり途方に暮れていたところ、猫の譲渡会の張り紙を見つけました。譲渡会に参加し、今は迎えた猫たちと幸せに暮らしています。
最近では土日に譲渡していただいたボランティア団体にお手伝いに行っており、猫を通じて新たなコミュニティも増えました。
もし、猫を飼いたいという気持ちがあるのであれば、どうか勇気を出して譲渡会に参加してみてほしいです。
一匹でも多くの猫が新しい家族に出会えることを願っています。


猫の譲渡会を開催します
動物愛護活動の一環として、譲渡ボランティア団体の方々と動物愛護センターが共同で、譲渡会を開催します。譲渡会会場に動物を連れてくることはご遠慮ください。
日時=7月20日(土曜)午後1時~4時
場所・会場=動物愛護センター東葛飾支所(柏市高柳1018-6)
内容=千葉県動物愛護センターの登録譲渡ボランティア団体(非営利団体)がそれぞれ保護収容している猫を会場に連れてきて、 猫を新たな家族として迎え入れたいと考えている希望者とマッチングします。
費用・料金=参加費無料(譲渡が決定した場合、団体によっては実費程度の費用の負担があります)。
申し込み・応募=6月24日(月曜)~7月19日(金曜)の平日午前8時30分~午後5時15分に動物愛護センター東葛飾支所TEL04-7191-0050

飼育マナーを守ろう
わんちゃん編

犬の散歩マナー
- 必ず処理袋を携行し、ふんは責任をもって飼い主が必ず持ち帰るようにしましょう。
- 他人の敷地や家の壁におしっこをさせないようにしましょう(トイレは自宅で済ませましょう)。
- リードをつけて散歩しましょう。
鳴き声が他人の迷惑にならないように注意しましょう
犬が頻繁にほえると周囲の人にとって迷惑になります。しつけの本から学ぶ、または、訓練士に相談しましょう。
ねこちゃん編
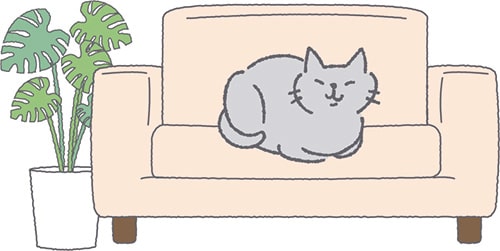
飼い猫
- 猫は屋内で飼いましょう
交通事故や感染症、猫同士のけんか、迷子などは屋内飼育で防ぐことができます。
地域猫
地域猫とは、地域住民の理解の下、適切に管理されている飼い主のいない猫のことです。地域猫活動は人と猫が共生していくための有効手段の1つです。
- 置き餌や、同意を得てない場所での餌やりはやめましょう
- トイレの設置や周辺の清掃などを行いましょう
- 増えないように不妊手術を実施しましょう
- 地域住民の理解を得ましょう
こんな制度があります
問い合わせ=TEL047-712-6309自然環境課
犬猫のフードなどの寄付を受け付けています
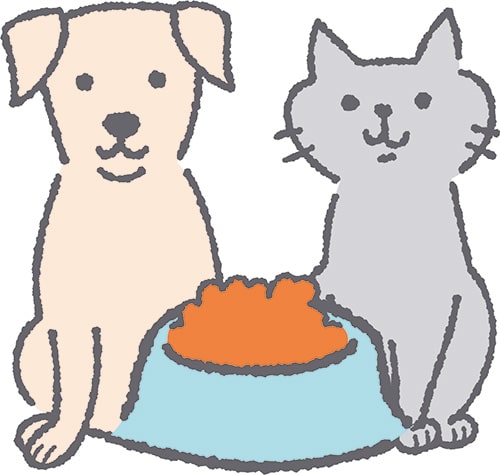
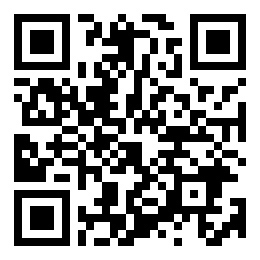
不要になった犬猫のフード、トイレ用消耗品の寄付を第2庁舎同課にご持参ください。未開封のもので、フードは賞味期限が6カ月以上残っているものが対象です。詳しくは右記2次元コードで確認してください。

飼い主のいない猫の不妊等手術費用など、マイクロチップ装着助成

迷惑被害を解決するため、地域猫活動の支援として、飼い主のいない猫の不妊等手術や入院検査などとマイクロチップ装着にかかった費用の一部を助成します。詳しくは右記2次元コードで確認してください。
飼い主のいない猫譲渡会費用及び保護猫管理費の助成
保護した猫の譲渡が成立したときに、譲渡するまでの期間にかかった餌代や物品の購入費の一部を助成します。
また、譲渡会開催に要した会場使用料と印刷製本費の一部を助成します。
いざという時は一緒に避難しましょう
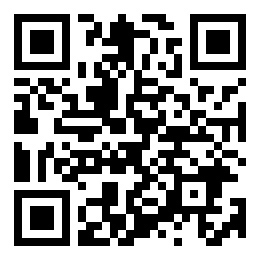
大規模な災害が発生すると、人間だけでなく、ペットも被災します。本市では災害時に一部の避難所にペットと同行・同伴避難することができますが、避難所での飼育は飼い主の責任となります。避難の際の注意点、日頃の備えなどの詳細は右記2次元コードで確認してください。
【6月は「食育月間」毎月19日は「食育の日」】
食べて健康 子どもから大人まで年代別に食事のポイントをご紹介
生涯にわたり心身ともに健康でいきいきと過ごすためには、年代に応じた生活習慣、食習慣を心がけて生活することが大切です。
本市では食育に関心を持っていただけるよう、食生活についての啓発活動や地産地消などさまざまな取り組みを行っています。
年代ごとの食事のポイントを参考にして、日々の生活でできることから始めましょう。
問い合わせ=TEL047-316-1036健康支援課
妊娠期
妊娠を機に、家族で食生活の見直しを

お母さんの健康と赤ちゃんのすこやかな発育には、妊娠前からの体づくりが大切です。葉酸、鉄、カルシウムなど、妊娠中に必要な栄養素が不足しないように、心がけましょう。
【参加してみよう】パパママ栄養クラス
おおむね6~8カ月の妊婦とパートナーを対象に、バランスの良い食事の話や、妊娠中に必要な栄養の取り方などをお伝えしています。
(こども家庭相談課)
乳幼児期【0~5歳】
よく噛(か)んで食べよう

噛む力を育てるには、食べ物をゆっくり噛んで味わうことが大切です。日々の食事の中に噛み応えのある食べ物を取り入れ、調理方法を工夫しましょう。また、毎日の食事中に、「これってどんな味」「今日のご飯おいしいね」などのちょっとした会話をすることで食べることへの興味が高まり、よく噛んで食べる力につながります。
【参加してみよう】離乳食教室
1回食(4~6カ月児)、2回食(7・8カ月児)を対象に離乳食の進め方の講話と、作り方の実演を行っています(7月 健康づくり・子育て(健診、教室、相談など)のお知らせを参照)。
(こども家庭相談課)
【取り組んでいます】保育園での食育
園庭やプランターで野菜の栽培を行い、収穫して給食で食べたり、家庭に持ち帰っています。また、クッキング保育や行事食にも取り組んでいます。
(幼保施設管理課)
学童期【6~12歳】~思春期【13~19歳】
成長期の子どもたちのために

特に栄養価では、カルシウムや鉄が不足気味となることがありますので、乳製品や乾物などを取り入れた料理がお勧めです。
【取り組んでいます】食品ロス削減の推進
食品ロス(まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品)を減らすため、家庭や学校で取り組める削減方法を出前授業を通して伝えています。
(清掃事業課)
栄養教諭、学校栄養職員による食育授業

子どもたちが自分の食べるものに興味を持ち、食事を楽しみ、苦手な食材にも挑戦できるよう、取り組んでいます。その一例として、小学校では、子どもたちがさやむきした「グリーンピース」を給食で提供し、昼の放送などで紹介しています。
(保健体育課)
青年期【20~39歳】
野菜を食べよう

学業や仕事、家庭のことなどで忙しい毎日、食事も偏りやすくなる年代です。特に野菜は不足しがちで、20~30代で1日の野菜の推奨量の350グラムを食べている人は、全体の約3パーセントです(令和5年度市民の健康に関するアンケート)。和え物や炒め物、具だくさんの汁ものなど、毎食1~2皿の野菜料理を食べましょう
【忙しい毎日に楽しみを 野菜を育ててみよう】ふれあい農園

「農業の大切さ」や「土に触れ作物を育てることの楽しさ」を知ってもらうために、野菜の植え付け・栽培・収穫体験の場を提供し、農業への理解向上を図っています。「子どもと楽しみながら収穫できた」など好評です。今年度の募集は7月下旬からを予定しています。
(農業振興課)
魚を食べよう
50代以降に比べ、若い世代は魚介類の摂取量が少ない傾向にあります。魚介類には良質なたんぱく質や動脈硬化予防が期待されるDHAなども含まれており、本市は、スズキ、ノリ、ホンビノス貝などの海産物に恵まれています。新鮮な地場産物を食べてみませんか。
【行ってみよう】市川産水産物の販売


市内鮮魚店での市川産水産物の販売や、いちかわ三番瀬まつりの開催などを行っています。6月21日(金曜)には、市川産のスズキを、市内鮮魚店で販売します(詳細は右記2次元コード参照)。
(臨海整備課)
壮年期【40~64歳】
塩分の取りすぎに注意

塩分の取りすぎは、高血圧になりやすく、心疾患などのリスクを高めます。
成人の1日の食塩摂取量の目安は男性7.5グラム未満、女性6.5グラム未満(2020年日本人の食事摂取基準)です。例えば、ラーメンには1食で約6グラムの塩分が含まれます。1日の目安量を超えてしまいがちです。適塩でおいしく食べるためには、だしのうまみや酸味、香りなどを活用する工夫が必要です。
【味わってみよう】世界のだしを使った料理
日本のだしはかつお節などの魚介類や、しいたけなどのきのこ類を使っており、あっさりとしていて香りが良く、食材の味を引き立てる特徴があります。西洋料理では、鶏ガラや野菜などからとるブイヨン、中華料理では豚骨や魚介類などを煮込む湯(タン)などがあります。一緒に煮込む食材や煮込み時間により、味が異なりますので、料理に合わせてさまざまなだしを使ってみましょう。

市公式Webサイトでは適塩レシピ(右記2次元コード参照)を公開しています。
高齢期【65歳以上】
たんぱく質を意識して、健康な体をつくろう

たんぱく質が少なくなると、筋肉が衰える原因になります。卵、肉、魚などたんぱく質を多く含む食品を意識して食べましょう。また、家族や友人、地域の方など、誰かと一緒に食事を楽しむことにより、おいしく感じられ、食欲増進にもつながります。
【旬の味覚を家庭でも簡単に】作ってみよう
グリーンピースごはん

材料(4人分)
米…2合
酒…小さじ1
塩…小さじ1/4
グリーンピース…20グラム
作り方
[1]米をといでおく。
[2]炊飯器に[1]とグリーンピースを入れ、2合の目盛り分まで水を加え、酒、塩を入れ炊く。
グリーンピース入り卵焼き

材料(4人分)
卵…2個
だし汁…大さじ1
塩…一つまみ
砂糖…小さじ2
グリーンピース…小さじ1
作り方
[1]ボールにだし汁、塩、砂糖を入れ、混ぜておく。卵を割りほぐす。
[2]ゆでておいたグリーンピースを[1]に混ぜ合わせる。
[3]卵を焼く。
食への関心を深めましょう
講座に参加してみよう
食育講演会、生活習慣改善講座も開催予定です。日程が近くなりましたら、広報いちかわや市公式Webサイトでお知らせします。
市川市食生活サポーターが伝えます
食生活の大切さを伝え、「食による健康づくり活動」を行っています。主な活動として、食育講習会の開催、おいしいレシピの作成があります。また、「早寝、早起き、朝ごはん」など食をテーマにした講義と調理実習を行う、「おやこの食育講習会」を地域で実施しています。ご希望の団体は、健康支援課へご連絡ください。
栄養バランスの良い食事をしよう
年代別の食事のポイントはいかがでしたか。全世代を通して毎日、朝、昼、夕の1日3食、主食(ごはん、パン、麺)、主菜(肉、魚、卵、大豆製品)、副菜(野菜、海藻、きのこ)をバランス良く食べることを心がけましょう。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市長公室 広報広聴課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 広報グループ
- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764
- 広聴・Webグループ
- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764
- 政策プロモーショングループ
- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764

