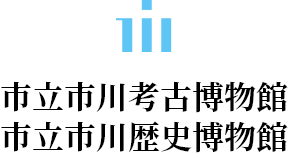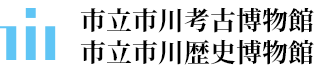文化財(県指定)柴田是真画連句額
柴田是真画連句額(しばたぜしんがれんくがく)

柴田是真(1807~1891)は、幕末から明治中期にかけて活躍した日本画家です。
蒔絵を学び、四条派の画風を鈴木南嶺(すずきなんれい)と岡本豊彦(おかもととよひこ)の門において体得しました。動きのある自由な筆運びと機知に富んだ表現には是真の個性がよく表れており、その俳趣あふれる画法は江戸後期の酒井抱一(さかいほういつ)に次ぐとも詳されています。
白幡天神社にある連句額の絵は、幅約57.5センチメートル、長さ198.5センチメートルという大きなケヤキの一枚板に、胡粉(ごふん、白色の顔料)彩色で梅の木と、竹竿の先に桶を付けたつるべを、板の上部へ大きく横長に描いたものです。黒ずんだ板から浮き上がるような絵は、写実的でのびのびとしています。
絵の下には連句が墨書きされ、末尾に「明治十有三年三月」とあるところから、是真74歳の作であることが分かります。
なお、木地に着色の絵を描いた是真の作品で、現存するものはわずか5枚。白幡天神社の額はそのうちの貴重な1枚です。

酒井抱一(さかいほういつ 1761~1828)
日本画家。狩野派、浮世絵、琳派などから幅広く絵を学び、尾形光琳の研究にも尽力しました。繊細で情感あふれる画法といわれています。
アクセス
- 住所
- 菅野1-15-2
- 交通
- 京成線八幡駅から徒歩8分
見学は、白幡天神社にお問い合わせください。
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市教育委員会 教育振興部 文化財課 文化財グループ
〒272-8501
市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第二庁舎 4階(文化財グループ)
- 電話
- 047-704-8137
- FAX
- 047-383-9263