更新日: 2025年12月2日
子ども医療費助成制度
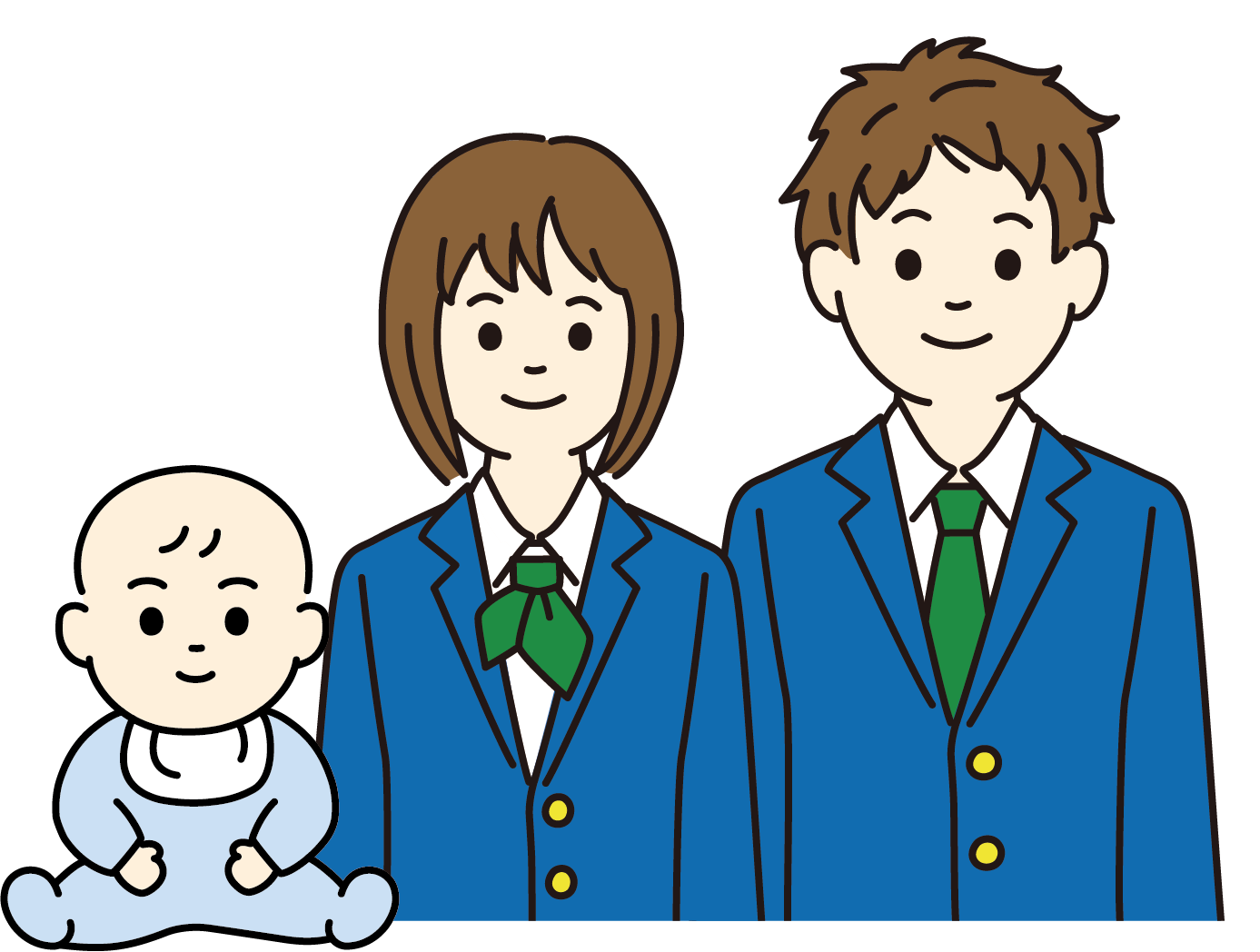
令和7年8月1日からの子ども医療費受給券について
令和7年8月1日から有効の新しい受給券は7月24日に送付。
よくあるご質問・お問い合わせについて

特にご質問・お問い合わせの多い内容をご案内しております。
下記リンクより、ご確認ください。
申請書ダウンロードは、こちらから
この制度は、市川市に住民登録があり健康保険に加入している、0歳から高校生相当年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんの健全な育成と保護者の経済的な負担の軽減のため、医療費の全部又は一部を助成するものです。

子ども医療費助成を受けるためには、登録申請が必要です。
助成対象となる方には「市川市子ども医療費助成受給券」を発行します。
助成の範囲
令和7年8月現在
| 対象年齢 | 0歳児~高校生相当年齢 (18歳に達する日以後の最初3月31日)までの子ども |
|---|---|
| 助成内容と自己負担金 | 入院1日300円 通院1回300円 調剤無料 同一医療機関で同一月の受診においては入院11日、通院6回以降は自己負担金無料 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
- ※市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯は、自己負担金の支払いはありません。
令和5年度中の制度改正
令和5年3月末診療分まで
| 対象年齢 | 0歳児~中学校修了 (15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども |
|---|---|
| 助成内容と自己負担金 | 入院1日300円 通院1回300円 調剤無料 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
- ※市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯は、自己負担金の支払いはありません。
令和5年4月診療分から
| 対象年齢 | 0歳児~高校生相当年齢 (18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども |
|---|---|
| 助成内容と自己負担金 | 入院1日300円 通院1回300円 調剤無料 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
- ※市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯は、自己負担金の支払いはありません。
令和5年8月診療分から
「月額上限」が開始し、★の内容で助成範囲が拡大となります。
※通院と入院は別々でカウントします。
| 対象年齢 | 0歳児~高校生相当年齢 (18歳に達する日以後の最初3月31日)までの子ども |
|---|---|
| 助成内容と自己負担金 | 入院1日300円 通院1回300円 調剤無料 ★同一医療機関で同一月の受診においては入院11日、通院6回以降は自己負担金無料 |
| 所得制限 | 所得制限なし |
令和5年11月診療分から
高校生相当年齢の現物給付(受給券での受診)が開始となります。
- ※令和5年4月以降の診療で、受給券がお手元になかった期間の受診については償還払いにて、お手続きください。(一部制限有り)
詳細は受給券を使用できなかった場合(償還払いの申請)を確認ください
医療費の助成を行うには、当該子どもの保護者の住民税等を確認する必要があります。
対象とならない医療費
健康保険が適用されないもの
(例)乳幼児健診料・健康診断料・予防接種料・薬の容器代・差額ベッド代・文書料・医療機関への交通費・大学病院等(200床以上)の初診時にかかる保険外の費用(紹介状がない場合にかかる料金)など
健康保険の高額療養費や附加給付または他の法令による医療費の助成等(未熟児養育医療など)を受けている場合は、その額を除いた分を助成します。
学校等でのけがについて
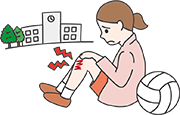
保育所や幼稚園、小学校~高校等の管理下におけるお子さんの負傷等(負傷、疾病等)に関しては、独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。災害共済給付の対象となる負傷等の場合、災害共済給付が優先されるため、子ども医療費助成受給券はご使用になれません。
受給券の申請方法(出生・転入等)

市川市子ども医療費助成登録申請書を提出し、当該子どもの保護者の住民税等の確認が取れましたら、『市川市子ども医療費助成受給券』(以下、受給券)を交付します。
出生や転入の場合は、児童手当の手続きについてもあわせてご確認ください。
受給券の発送時期は、申請受付日によって異なります。(お子様の住所宛に郵送します。)
| 申請受付日 | 受給券の発送時期 | 有効期間開始日 |
|---|---|---|
| 1日~15日 | 当月末 | 出生 →出生から有効期間開始 転入(海外転入なども含む) →ご申請の翌月1日から有効期間開始 |
| 16日~月末 | 翌月の中旬 | 出生 →出生から有効期間開始 転入(海外転入なども含む) →ご申請の翌月1日から有効期間開始 |
- ※受給券の申請日が7月1日以降でお子様が7月末までに出生した方は 受給券に印字される、有効期間開始日が8月1日となります。
例1)7月1日出生 → 7月5日申請 → 7月末に発送 有効期間開始日8月1日
例2)7月16日出生 → 7月20日申請 → 8月中旬に発送 有効期間開始日8月1日
ご希望の方には、出生日から7月31日までの受給券を交付いたします。
詳細はよくあるご質問・お問い合わせについて Q8をご確認下さい。
住民登録後、受給券の有効期間開始前の医療費については償還払いの申請をご覧ください。
「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」が発行された児童は「子ども医療費助成受給券」が使用できませんのでご返却ください。
申請に必要なもの
(1)市川市子ども医療費助成登録申請書

- 郵送での手続きも可能です。 ⇒市川市子ども医療費助成登録申請書
- 申請書記載方法については、市川市子ども医療費助成登録申請書の郵送手続きについて(PDFファイル)をご覧ください。
(2)子どもの健康保険情報がわかるもの
資格確認書・マイナポータルの画面※子どもが加入する予定の保護者の健康保険情報がわかるものでも可
(3)保護者名義の口座がわかるもの
ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
(4)保護者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート) 等
(5)保護者のマイナンバー確認書類
マイナンバーカード、通知カード 等
(6)保護者の所得確認について
受給券の交付には、保護者の所得確認が必要になります。
その年の1月1日時点に、住民票のある自治体で市県民税が課税されるため、転入等により市川市課税でない場合は、以下の手続きが必要になります。
- マイナンバー制度による地方税関係情報の情報連携を希望する場合(推奨)
(1)「市川市子ども医療費助成登録申請書」上部のマイナンバー使用欄にチェックをいれず、申請書を提出ください。(マイナンバーカードをお持ちでない方もご利用できます)
※自治体間で市県民税の確認を行います。 - マイナンバー制度による地方税関係情報の情報連携を希望しない場合
ご自身で市県民税課税証明書の取得及び提出が必要になります。
必要年度については、取得前に子育て給付課にお問い合わせください。- ※源泉徴収票、市県民税決定通知書は証明になりません。
- ※1月1日時点で海外居住の方は、別途書類(戸籍の附票やパスポートのコピー等)が必要になる場合があるため、子育て給付課にお問い合わせください。
- ※特例適用配当・利子、条約適用配当・利子等の所得がある方は、お申し出ください。
受給券の使用方法
千葉県内の医療機関で受診する際に『市川市子ども医療費助成受給券』と健康保険情報がわかるものを医療機関の窓口に提示すると、保険適用分については自己負担金のみの支払いとなります。
この方式を「現物給付」といいます。
「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」が発行されたお子さんは「子ども医療費助成受給券」が使用できませんのでご返却ください。
入院等で医療費が高額になる場合は
加入している健康保険組合等から「限度額適用認定証」の発行を受けてください。
「限度額適用認定証」については、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。
受給券の更新について
受給券は、毎年8月1日から自己負担金(0円または300円)を決定する住民税等の基準年度が変わります。
保護者の新年度住民税等の確認が取れたお子さんには、毎年7月下旬に新しい受給券を送付します。
下記に該当する方は、税申告を求めることがあります
- 年末調整や確定申告で配偶者の扶養が漏れている場合
- 産育休を取得されている方で、職場から給与支払報告書の提出がない場合
- 住民票は市川市だが、居住の実態が海外にある場合
申告についてのお問い合わせは、市川市市民税課にお願いします。
受給券を使用できなかった場合(償還払いの申請)
県外や県内の受給券の取り扱いのない医療機関での受診など、受給券を使用できなかった場合には申請をすると、指定した保護者名義の口座に助成金を振り込みます。
(令和5年8月診療分以降で月額上限の適用をご希望の場合は、1か月分全ての領収書を、まとめて申請してください。)
この手続き方法を「償還払い」といいます。
手続きの流れ

- 医療機関の窓口で健康保険情報がわかるものを提示し、領収書を受け取ってください。
- 下記の《申請の窓口》にて申請の手続きをしてください。郵送での手続きも可能です。
- 指定した保護者名義の口座に助成金を振り込みます。(原則として、申請の2ヵ月後の月末(※))
申請期間:医療費を支払った翌月から2年間(医療費を受診した翌月以降に申請してください。)
(例)令和7年8月に支払った分は、令和9年8月末日まで申請が可能です。
申請に必要なもの
1.市川市子ども医療費助成金交付申請書
申請をするときに、下記の《申請の窓口》でお渡しします。
ダウンロードして利用することも可能です。
2.領収書 (受診した子どもの氏名・保険点数・診療年月日が明記されたもの)
領収書は原本が必要です。(コピーのみでは受付ができません。)
領収書の返却を希望する場合は、原本とコピー(両面コピーは不可)をご提出いただくと原本に「子ども医療費申請済」の印を押して返却します。
なお、全国健康保険協会にご加入の方で同月内に21,000円(7,000点もしくは10,500点)以上の医療費を申請される時は、高額療養費の支給決定通知又は不支給決定通知の提出が必須となります。
小児慢性特定疾患医療費助成制度や自立支援医療(育成医療)等のその他の公費負担医療制度が適用される場合は、その受給者証や自己負担上限額管理ノート等(コピー可)を添付し申請してください。
市川市子ども医療費証明書でご申請いただく方は、こちらよりダウンロードをしてください。(領収書を紛失した場合等)
3.子どもの健康保険情報がわかるもの
4.保護者名義の口座が分かるもの
5.市川市子ども医療費助成受給券
郵送での申請方法
申請書(記載方法については、子ども医療費助成金交付申請書の郵送手続きについて(PDFファイル)をご覧ください)、受診者の保険情報がわかるもののコピー、領収書の原本を子育て給付課までご郵送ください。
届け出が必要な場合
(1)市川市子ども医療費助成登録申請事項変更届が必要な場合。郵送での手続きも可能です。
- 子どもまたは保護者の住所に変更があったとき
- 子どもの氏名に変更があったとき
- 加入している健康保険に変更があったとき(郵送で届出する際は、健康保険情報がわかるもののコピーを添付してください)
- 離婚・婚姻(事実上の婚姻も含む)・死亡などにより、保護者に変更があったとき
- 修正申告等により、保護者の税額や所得に変更があったとき
市川市子ども医療費助成登録申請事項変更届(記入例)(PDFファイル)
(2)市川市子ども医療費助成受給券返納届が必要な場合。郵送での手続きも可能です。
- 子どもが転出したとき
- 受給券の有効期間が満了したとき
- 子どもの監護を終了したとき
- 子どもが死亡したとき
※受給券の返却も併せてお願いします。
受給券を紛失・破損したとき(再交付の申請)

受給券を紛失、破損したときは、再発行が可能です。
《申請の窓口》に保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちいただければ窓口で即日発行します。
また、郵送での手続きも可能です。
ダウンロードして利用することも可能です。
※受給者番号がわからない時は、番号の記載は不要です。
よくあるご質問・お問い合わせについて
Q1 子どもが県外の病院を受診したので、病院ではマイナ保険証を使って支払いをしました。(2割または3割の保険自己負担分)医療費の還付はできますか?
A1 お子様が受給券を使わずに支払われた医療費(保険適用分)につきましては、病院の領収書を添付して申請をしていただければ、保護者名義の口座に振込みをする償還払いで助成を行わせていただきます。
受給券を使用できなかった場合(償還払いの申請)より、お手続き内容をご確認ください。
Q2 子どもが病院を受診するのですが、受給券が見当たりません。窓口で即日再発行していただくことは可能ですか?
A2 窓口にお越しいただき、お子様の健康保険情報のわかるものをお持ちいただければ、市川市子ども医療費助成受給券再交付申請書をご記入の上、受給券を即日再発行いたします。
受給券を紛失・破損したとき(再交付の申請)より、お手続き内容をご確認ください。
Q3 小児弱視用のメガネ、コルセットなどの治療用装具を購入しました。医療費の申請はどのように行えばよいですか?
A3 手続きの流れについて説明します。
- 治療用装具の領収書(10割負担)を用意してください。
- ご加入の保険組合等に、その領収書を添付して療養費の支給申請を行い、保険給付(7割又は8割)を受けてください。
(領収書の原本を提出する場合は、必ず領収書のコピーを取ってください。) - 保険組合から発行された「療養費等支給決定通知書」、「治療用装具の領収書(コピー可)」を持って、償還払いの申請を行ってください。
全国健康保険協会にご加入の方
治療用装具の領収書(10割負担)から保険給付(7割又は8割)を引いた額が、21,000円を超えている場合は、その金額に対しての高額療養費の申請をしていただき、全国健康保険協会から発行される「高額療養費支給決定通知書」または「不支給通知書」も併せてご提出ください。
Q4 在宅診療、オンライン診療等を受診したが、領収書がスマホでしか確認できない。医療費の償還払いはできますか?
A4 償還払いを行うには、病院の印が押された領収書(受診日、受診者、保険点数、領収金額が記載)が必要になります。そのため、医療機関にお問い合わせいただき紙の領収書を発行してもらってください。
Q5 領収書の原本を確定申告で使いたい。原本を返却してもらえますか?
A5 窓口で申請をされる場合は、領収書の原本とコピー(両面コピー不可)をお持ち頂ければ、領収書の原本に『子ども医療費申請済』の印を押して返却いたします。郵送で申請される場合は、返信用封筒(切手付)も併せてお送りください。
Q6 今までひとり親でしたが、婚姻することになりました。何か手続きが必要ですか?
A6 子ども医療費助成制度は、お子様の養育をする方を保護者(婚姻前の同居等も含む)として登録をしております。お子様の保護者情報の変更を行うため、市川市子ども医療費助成登録申請事項変更届の提出が必要になります。
届け出が必要な場合より、手続き内容をご確認ください。
「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」をお使いの方につきましては、子育て給付課までご返却ください。新しい「子ども医療費助成受給券」は、手続き内容の確認が取れ次第、お送りします。
Q7 7月出生ですが、有効期間開始日が8月1日~の受給券が届きました。7月中の医療費は助成対象外でしょうか?
A7 受給券の有効期間終了日は原則、毎年7月31日です。そのため、出生日~7月31日までの受給券を7月末に送付しても、期限切れのため送付しておりません。
しかし、出生日から市川市に住民登録があれば、医療費は助成対象になるため、
受給券を使用できなかった場合(償還払いの申請)の手続きをお願いします。
また、出生日~7月末の受給券を交付希望の方は、登録申請書余白に「出生日~7月31日までの受給券を希望します」と記入していただくか、下記連絡先までご一報下さい。
Q8 子どものみ市外の学生寮に引っ越ししたため、住民票を異動しましたが、市川市医療費助成は対象外ですか?
A8 転出日をもちまして、市川市の子ども医療費助成の受給資格は消滅します。転出後の医療費助成制度については、転入先の自治体にお問い合わせください。なお、転入先の自治体で医療費助成制度が利用できない場合は、子育て給付課までご連絡ください。
申請の窓口
| 申請の窓口 | 平日開庁時間 | その他開庁時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市川市役所子育て給付課 | 午前8時45分~午後5時15分 | |
| 2 | 行徳支所福祉課 | 午前8時45分~午後5時15分 | |
| 3 | 大柏出張所 | 午前8時45分~午後5時15分 | |
| 4 | 南行徳市民センター | 午前8時45分~午後5時15分 | |
| 5 | 市川駅行政サービスセンター | 午前8時45分~午後8時00分 | 土曜日のみ 午前8時45分~午後5時 |
1~4の手続き窓口は、平日のみの開庁となります(祝日、年末年始は閉庁しています)。
市民課窓口連絡所(信篤、国分、中山)では、手続き出来ません。
医療機関の適正受診にご協力をお願いいたします
近年、軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来を受診する方が多い状況です。
このため、救急外来が混み合い、緊急性の高い重症患者の治療に支障をきたすことが心配されます。
必要な人が安心して医療を受けられるように、医療機関の適正受診にご協力をお願いいたします。
1.市民の方の相談に、医師、保健師、看護師などが対応していますので、急な病気などでお困りの際に、ご利用ください。
あんしんホットダイヤル 24時間年中無休(通話料は無料)※市川市
- 電話
- 0120-241-596
- FAX
- 0120-637-119
利用方法 あんしんホットダイヤルは、電話番号を通知する設定にしてからご利用ください
(非通知設定ではご利用できません)。
こども急病電話相談 毎日・夜間 午後7時~翌午前8時 (通話料は有料)
プッシュ回線の固定電話・携帯電話からは、局番なしの #8000
ダイヤル回線からは 043-242-9939
- 実施
- 千葉県
- 運営
- 千葉県医師会
2.ジェネリック医薬品を上手に利用しましょう。
ジェネリック医薬品は新薬と同等の効果があり、新薬より低価格です。
3.市川市急病診療所のご案内
市川市急病診療所の紹介ページへジャンプします。

