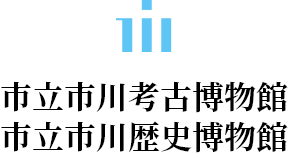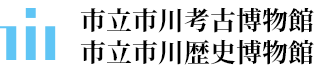文化財(県指定)梵鐘[元亨元年在銘]
梵鐘[元亨元年在銘] (ぼんしょう げんこうがんねんざいめい)
寛政5年(1793)1月19日、葛飾八幡宮社殿西側にあったケヤキの枯木が大風で倒れ、その根元から掘り出されたのがこの梵鐘です。総高117.2センチメートル、口径66.7センチメートルで、池の間(いけのま、銘文を記す空地)の上下にある型継の跡から、3段組で鋳上げ、さらに笠型を継いで作られたことが分かります。乳は4段5列、上帯、下帯はどちらも模様のない素文です。龍頭(りゅうず、梁に吊るすための梵鐘の頭部を龍の頭の形にした部分)の向きと平行に2つの撞座(つきざ、鐘を撞くところ)があり、8葉単弁の蓮の花が意匠されています。そして池の間第1区と第2区には次のような陰刻銘があります。

-
第2区
- 元亨元年辛十二月十七日
- 酉
- 願主右衛門尉丸子真吉
- 別當法印智圓
-
第1区
- 敬
- 奉冶鋳銅鐘
- 大日本東州下総第一鎮守
- 葛飾八幡是大菩薩傳聞寛平
- 宇多天皇勅願社壇建久以来
- 右大将軍崇敬殊勝天長地久
- 前横巨海後連遠村魚虫性動
- 鳬鐘暁聲人獣眠覺金啓夜響
- 求除煩悩能證菩提
中ほどの「前横巨海後連遠村」により、八幡宮が海を前にして建っていた当時の状況が分かります。元亨元年は西暦1321年にあたり、梵鐘鋳造の年です。また、笠の部分にはタガネでひっかいたような細字で、「応永二十八年三月廿一日」の銘がありますが、これについては諸説があって、何を示すのか明らかではありません。

梵鐘(ぼんしょう)
龍頭の方向と撞座の位置が直角になっているものが古い形ですが、この梵鐘は他の特徴からみても、鎌倉時代の様式を示す新しい形式です。
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市教育委員会 教育振興部 文化財課 文化財グループ
〒272-8501
市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第二庁舎 4階(文化財グループ)
- 電話
- 047-704-8137
- FAX
- 047-383-9263