温まろう(温泉と文学)
特集1: 温泉ゆかりの文人墨客

由緒ある古い温泉地に行くと、明治・大正・昭和の文人たちの足跡を見かけることありませんか。例えば文学碑が建立、記念館が建設されていたり、温泉宿に「文豪○○先生執筆のお部屋」が当時のまま保存されていることもあります。温泉地に来る観光客のなかには、こうした文人のゆかりを訪ねて来る方も少なからずいるようです。
文人墨客たちは何故、湯治場を好んで訪れたのでしょう。第一の理由として、「原稿を書く静かな環境をもとめた」すなわち執筆の場、第二の理由として「小説舞台として温泉の鄙びた地を選んだ」、そして最後の理由、現代人にも通ずる「湯治療養のため」が大きな理由のようです。第二の理由に付随しますが、その温泉地が生まれ故郷だから小説舞台として選んだという文人もいます。
今回の特集では、いくつかの主要温泉と文人の関係をあらわした日本地図を掲示しました。その過程でできたささやかな温泉と文人墨客データベースをご紹介いたします。検索の際は、漢字(表記形:例「夏目漱石」など)でお願いします。
今後も「温泉を舞台とした作品」や「文人たちの足跡があるお宿」をもしご存知でしたら、ぜひお知らせください。
- ※この特集展示は、2004(平成16)年1月から2月にかけて、中央図書館で開催されました。
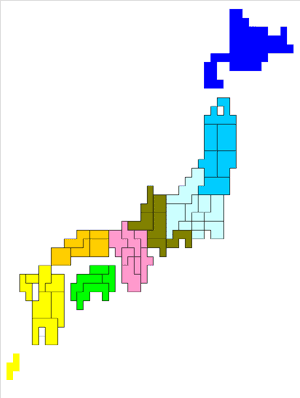
特集2:あなただけのお気に入りの温泉をみつけよう
寒い冬や仕事に疲れたあなたが、くつろいであたたまることができるお気に入りの温泉宿をみつけましょう。
「名作を生んだ宿」
矢島 裕紀彦とサライ編集部/編 小学館
今回の特集のタネ本。最近では小説家先生たちはホテルで缶詰にされて原稿を書かされると聞きますが、昔の文豪たちは、自ら旅に出て執筆。全25名の作家たちゆかりの宿を紹介。作家ゆかりの品や原稿などの写真も多数収録。
「温泉教授・松田忠徳の日本百名湯」
松田忠徳/著 日本経済新聞社
札幌国際大学観光学部教授で温泉文化論を講義している著者が選ぶ日本百名湯。同じ著者の「温泉教授の温泉ゼミナール」(光文社新書)では、ホンモノの温泉の見分け方、温泉をより楽しむための知識をわかりやすく紹介。
特集3:温泉に関する情報源リンク集
「温泉に関係することば大辞典」として約1300語を収録。小学館刊行の「日本国語大辞典」から湯ことばを200語をベースとして、その後は温泉関係や公衆浴場、民俗学、風俗学などの諸文献から収録。また「温泉文献目録」では温泉に関する文献を約200冊を評価解説しており圧巻です。
医療、環境、施設等、温泉保養地に関わるあらゆる分野における専門家を中心とした団体です。世界の温泉地データも扱っています。
このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市教育委員会 教育振興部 図書館課
〒272-0015
千葉県市川市鬼高1丁目1番4号 生涯学習センター内
- 電話
- 047-320-3333(自動応答)
047-320-3346(直通)



