中央図書館特集展示2013年
- イベント
中央図書館の特集展示コーナーでは、毎回さまざまなテーマを取りあげて、広く本の紹介を行っています。
- 2013年12月~2014年1月:知性と品格
- 2013年11月~12月:戦国武将・軍師から学ぶ
- 2013年10月~11月:“働く”を考える
- 2013年9月~10月:心の健康と自殺予防
- 2013年8月~9月:市川の文学:小説編
- 2013年7月~8月:民族と領土
- 2013年6月~7月:国際キヌア年
- 2013年5月~6月:動物と暮らす
- 2013年4月~5月:はじめの一歩
- 2013年3月~4月:和の美・和の技・和の心
- 2013年2月~3月:科学と暮らし
- 2013年1月~2月:日本と日本人のルーツを求めて
それぞれの資料リストは、Webサービスメニューの「特集展示資料一覧」で見ることができます。
知性と品格(12~1月)
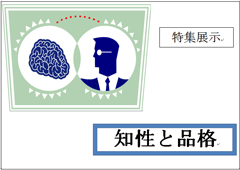
現代人に求められる知性と品格とはどのようなものでしょうか。
林望は『知性の磨きかた』で「知性とはそも何であるか・・・極的にいってしまえば、ものの見方なんです」と記し、佐々木正人は『知性はどこに生まれるか』で「水や土や光について、脳ではなく手や足や皮膚が持つ知性とは何だろう」と問う。尾田幸雄は『品格の原点』で明治人の生き方を問うた[『日本道徳論』を訳した。他方、島村洋子は『「品格バカ」が多すぎる』で、「品格なくてもいいでしょう」と記しました。
皆さんは、現代社会に求められる価値をどのように考えますか。
戦国武将・軍師から学ぶ(11~12月)
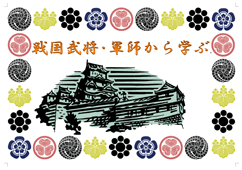
群雄割拠の戦国時代、日本の覇者を目指し、様々な戦略を駆使して乱世を勝ち抜いてきた戦国武将たち。
信玄、家康など主要な武将から、千葉県にゆかりのある里見氏、次期大河ドラマでスポットを浴びる黒田官兵衛まで、その生き様や戦い方などを通して、現代を生きる私たちにも活かすことのできる知恵や、リーダーシップを学ぶと共に、戦国武将たちの素顔に触れてください。
“働く”を考える(10~11月)
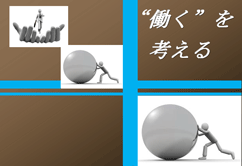
幼いころからの夢はあきらめたくない、もう一度社会に出たい、子育てとうまく両立させたい、楽しくやりたい・・・
「仕事」に込められた思いや希望は人それぞれです。
また、様々な悩みや疑問も、「仕事」にはつきものです。
今回は「働く」について考える本を集めてみました。
それぞれの仕事や働く環境を今一度考えてみてはいかがでしょうか。
心の健康と自殺予防:自殺予防週間にちなんで(9~10月)
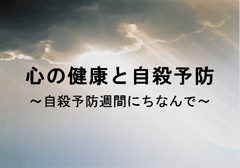
困ったときは、ひとりで悩まず 相談しよう
9月10日は、WHO(世界保健機関)の「世界自殺予防デー」。そして、9月10日から9月16日は国の「自殺予防週間」です。
日本の年間自殺者数は、平成10年から14年連続して3万人を超え、大きな社会問題になっています。
市川市では「困ったときは、ひとりで悩まず 相談しよう」を今年の自殺予防週間のキャッチフレーズとして、私たち一人ひとりが自殺や精神疾患を正しく知り、誤解や偏見をなくし、命の大切さを考え、自殺の危険を示すサインや危険に気づいたときの対応方法等を知るためのさまざまな活動を行っています。
9月から10月の特集コーナーでも、市川市保健センター及び千葉県市川健康福祉センター(市川保健所)とも連携し、この問題を考える手助けとなる資料を集めてみました。
市川の文学:小説編(8~9月)
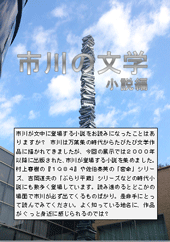
市川が文中に登場する小説をお読みになったことはありますか?
市川は万葉集の時代からたびたび文学作品に描かれてきましたが、今回の展示では2000年以降に出版された、市川が登場する小説を集めました。
村上春樹の『1Q84』や佐伯泰英の「密命」シリーズ、吉岡道夫の「ぶらり平蔵」シリーズなどの時代小説にも数多く登場しています。
読み進めるとどこかの場面で市川が必ず出てくるものばかり。
是非手にとって読んでみてください。
よく知っている地名に、作品がぐっと身近に感じられるのでは?
展示リストを作成しました。市川の言及箇所がわかります。
図書館ホームページの「市川の文学データベース」では、2000年以前に出版されたものも含めて、市川市を描いた作家と、市川市に関係する文学作品を調べることができます。
あわせてご覧ください。
これ以外にも市川が舞台になっている小説をご存知でしたら、ぜひ図書館までお知らせください。
民族と領土(7~8月)
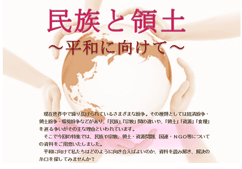
平和に向けて
現在世界中で繰り広げられているさまざまな紛争。その種類としては経済紛争・領土紛争・環境紛争などがあり、「民族」「宗教」間の違いや、「領土」「資源」「食糧」を巡る争いがその主な理由といわれています。
そこで今回の特集では、民族や宗教、領土・資源問題、国連・NGO等についての資料をご用意いたしました。
平和に向けて私たちはどのように向き合えばよいのか、資料を読み解き、解決の糸口を探してみませんか?
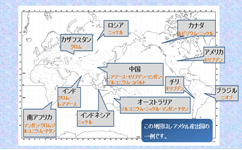
資源の確保
IT産業の発展には欠かせない重要な鉱物資源でありながら希少な希土類元素は、日本ではレアメタルと呼ばれます。
「レアアース(電池・ハードディスク・永久磁石)」や、「ニッケル(ステンレス銅、めっき、硬貨)」、「コバルト(携帯電話やパソコンに使用されるリチオムイオン二次電池)」などがこれにあたります。
これらの鉱物資源は、産出国に極端な偏りがあるため供給が安定せず、ここ数年で価格が数倍に上がったものもあります。
国際キヌア年(6~7月)
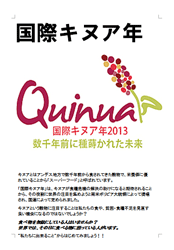
数千年前に種蒔かれた未来
キヌアとはアンデス地方で数千年前から食されてきた穀物で、栄養価に優れていることから「スーパーフード」と呼ばれています。
「国際キヌア年」は、キヌアが食糧危機の解決の助けになると期待されることから、その役割に世界の注目を集めようと南米ボリビア大統領によって提唱され、国連によって定められました。
キヌアという穀物に注目することで、私たちの食や貧困・食糧不足を見直す良い機会になるのではないでしょうか?
世界では、その日の食べ物にも困っている人がいます。
私たちに出来ることからはじめてみませんか?
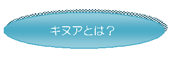
キヌアはホウレン草と同じアカザ科アカザ目の植物で、ボリビアからペルーまでを原産地とし、収穫時期になると色とりどりの穂を実らせます。
この実を脱穀したものを、アンデス地方では数千年前から主食としてきました。この穀物は味にくせがなく様々な料理に用いることができ、粥のようにして食べたり、茹でてサラダの添え物にしたり、スープに入れて食べることも出来ます。白米と混ぜて炊くともちもちとした食感が楽しめます。
栄養価は極めて高く、白米と比較するとタンパク質は2倍、カルシウムと食物繊維は6倍、鉄分は9倍にもなります。
また、厳しい環境でも育てることができるため、この穀物が普及することで食糧危機の解決につながるなど様々な可能性を秘めた穀物といわれています。
動物と暮らす(5~6月)
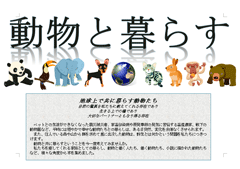
地球上で共に暮らす動物たち
自然の驚異を私たちに教えてくれる存在であり
生きる上での糧であり
大切なパートナーともなり得る存在
ペットとの生活ができなくなった震災被災者、家畜伝染病や原発事故の発生に苦悩する畜産農家、戦下の動物園など、平時には穏やかで幸せな動物たちとの暮らしは、ある日突然、変化を余儀なくさせられます。また、住んでいる森や山から餌を求めて里に出没した動物は、野生とは何かという問題を私たちにつきつけます。
動物と共に暮らすということを今一度考えてみませんか。
私たちを癒してくれる家族としての暮らし、動物と働く人たち、働く動物たち、小説に描かれた動物たちなど、様々な角度から本を集めました。
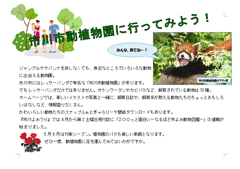
市川市動植物園に行ってみよう!
身近なところでいろいろな動物に出会える動物園。市川市にはレッサーパンダで有名な「市川市動植物園」があります。
でもレッサーパンダだけではありません。オランウータンやカピバラなど、飼育されている動物は70種。
ぜひ一度、動植物園に足を運んでみてはいかがですか。
はじめの一歩(4~5月)

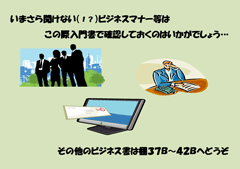
新年度が始まるこの季節、何か新しいことを始める絶好のチャンスです。
皆様のはじめの一歩を応援すべく、趣味、教養、自己啓発など、気軽に読める入門書ばかりを集めました。
まずは何から始めよう・・・
なんだかワクワクしてきませんか?
和の美・和の技・和の心(3~4月)

日本人が古来より育み、継承してきた「和」の文化は、艶やかで均整のとれた美しさ、職人の手から生み出される緻密な技術、そして礼儀や作法を重んじる清らかな心持によって成り立っています。
今回の特集では、「和」の美・技・心に関する資料を、様々な分野から集めました。
現代に生きる私たちが次の世代へと受け継いでいきたい「和」の文化の一端に触れてみませんか。
科学と暮らし(2~3月)
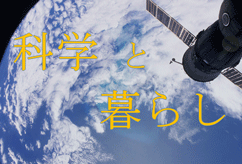
1963年、日米間の衛星テレビ中継実験が成功し、日本初の原子力発電も行われました。また、化学物質の危険性が認識されだしたのもこの頃でした。
それから50年、科学は暮らしを支え、豊かにしましたが、環境汚染などの、生活を脅かす側面も持っています。
科学は私たちの暮らしとどのように関わってきたのでしょうか。
暮らしに関わりのある科学の本や、科学技術の暮らしへの恩恵や影響について書かれている本を幅広く集めました。
日本と日本人のルーツを求めて(1~2月)

私たちが生まれ育つ「日本」、そして私たち「日本人」はどのようにして生まれたのでしょう。
日本に現存する最古の書物である『古事記』には、イザナギ・イザナミという男女二神が結ばれ、淡路島・四国と次々に島を産み日本の国土を創りだす「国生み」という神話が記載されています。
考古学において、日本列島に人が居住するようになった時期は二十万年以上前、氷河時代に今の日本列島とアジア大陸が海面低下により陸続きとなった頃、移住してきたといわれています。
また「日本」という国号は、『旧唐書(くとうじょ)』(945年成立)に「日本国は倭国の別種なり。其の国日辺にあるを以って、故に日本を以って名と為す。
或いは曰う、倭国自らその名の雅ならざるを悪(にく)み、改めて日本と為すと。
或いは云う、日本は旧小国、倭国の地を併せたりと。~」
と記載されており、倭国と日本国を併記した上で、日本国は倭国の別種とし、倭国が日本号へ変更した理由を記しています。
図書館の資料を紐解き、古代日本へと思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
特集展示アーカイヴ(過去の展示履歴保管庫)
このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市教育委員会 教育振興部 図書館課
〒272-0015
千葉県市川市鬼高1丁目1番4号 生涯学習センター内
- 電話
- 047-320-3333(自動応答)
047-320-3346(直通)
