真間のつぎはし
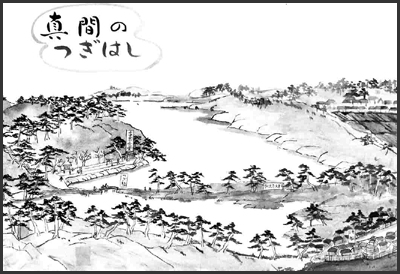
- 中津攸子/文
- 日本ペンクラブ会員
- 俳人協会会員
- 大衆文学研究会会員
- 歴史研究会会員
- NHK文化センター講師
- 竹早教員養成講師
- 和爾 寛子/絵
- 童画芸術協会会員
- 創竜会会員
- 貞静学園保育専門学校講師
- 市川民話の会会員
- 日本児童文学者協会会員
「真間のつぎはし」は全12枚の、絵葉書サイズの資料です。
市川市のホームページを開設した1997年から、許諾を得て掲載されてきました。
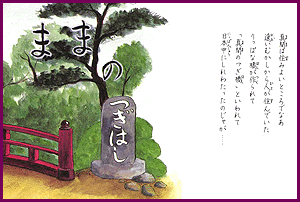
真間は住みよいところでな
遠いむかしから人が住んでいた
りっぱな橋が作られて
「真間のつぎ橋」といわれて
日本中に知れわたったのじゃが.................

むかし むかしの ことじゃがな
真間山の 下まで 海じゃった
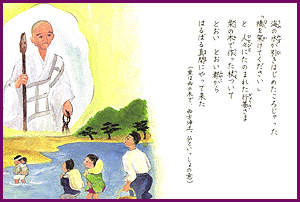
海の水が引きはじめたころじゃった
「橋を架けてください」
と人びとにたのまれた行基さま
栗の木でつくった杖について
とおいとおい都から
はるばる真間にやって来た
(栗は西の木で、西方浄土。仏といっしょの意)
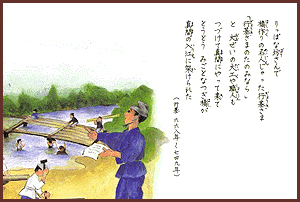
りっぱな坊さんで
橋作りの名人じゃった行基さま
「行基さまのたのみなら」
と大ぜいの大工や職人も
つづけて真間にやって来て
とうとう みごとなつぎ橋が
真間の入江にかけられた
(行基 668年~749年)
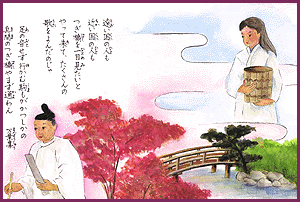
遠い国の人も
近い国の人も
つぎ橋を一目見たいと
やって来て、たくさんの歌をよんだのじゃ
足の音せず行かむ駒もがかつしかの
真間のつぎ橋やまず通わん万葉集
(万葉集は日本一古い歌の本)
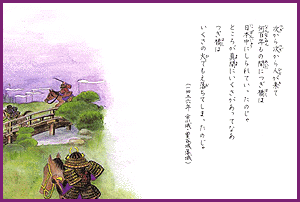
次から次から人が来て
何百年もの間につぎ橋は
日本中にしられていったのじゃ
ところが真間にいくさがあってなあ
つぎ橋は
いくさの火でもえ落ちてしまったのじゃ
(1456年 市川城・曽谷城落城)
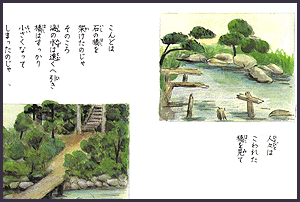
人びとはこわれた橋を見て
こんどは石の橋を架けたのじゃ
そのころ
海の水は遠くへ引き
橋はすっかり小さくなってしまったのじゃ
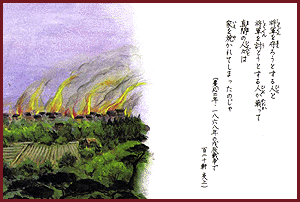
将軍を守ろうとする人と
将軍を討とうとする人が戦って
真間の人びとは
家を焼かれてしまったのじゃ
(慶応2年、1868年の戊辰戦争で120軒炎上)
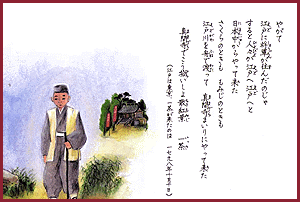
やがて
江戸に将軍が住んだのじゃ
すると人びとが江戸へ江戸へと
日本中からやって来た
さくらのときも もみじのときも
江戸川を舟で渡って
真間寺まいりにやって来た
真間寺でこ拾いしよ散紅葉 一茶
(江戸は東京、一茶が来たのは 1798年10月10日)
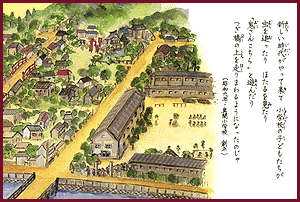
新しい時代がやって来て
小学校の子どもたちが
虫を追ったりほたるを見たり
「鬼さんこちら」と遊んだり
つぎ橋の上を
走りまわるようになったのじゃ
(昭和9年 真間小学校 創立)
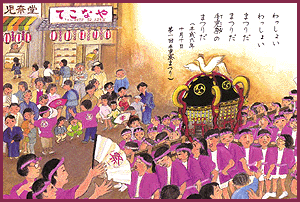
わっしょいわっしょい
まつりだまつりだ
手児奈のまつりだ
(平成6年10月10日 第1回手児奈まつり)
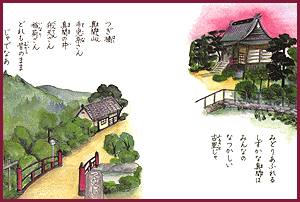
みどりあふれるしずかな真間は
みんなのなつかしい古里じゃ
つぎ橋真間山手児奈さん
真間の井 弁天さん 稲荷さん
どれも昔のままじゃでなあ
このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市教育委員会 教育振興部 図書館課
〒272-0015
千葉県市川市鬼高1丁目1番4号 生涯学習センター内
- 電話
- 047-320-3333(自動応答)
047-320-3346(直通)
